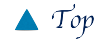🕰 西暦600年代の世の中はどんな感じ?
西暦600年代。この時代、世界史の舞台はどんな感じ? 世界は大きな変動の渦中にありました。 主な出来事を見てみましょう。 ・ ・まずは、ヨーロッパの東ローマ帝国……。 東ローマのビザンティン帝国は、長い間、東地中海地域で存在感がありましたが、この時期には多くの領土を失い、ここから少しずつ衰退の道を歩み始めました。 それはなぜ? イスラム教が誕生したのです! マホメットが登場して、聖典とともにイスラム教を創始。 アラーの神を支持する新勢力は、あれよあれよという間にアラビア半島を統一し、その影響力は中東、北アフリカまでおよびました。 元々、ヨーロッパと地中海周辺はキリスト教が大きな力を持っていたのですが、イスラム教の登場で、緊張感がピーンと高まります。 なぜなら、イスラム教とキリスト教は、ともに一神教なので、お互い、自分たちの〝神〟は譲れない。 宗教観の違いだけでなく、聖地エルサレムを巡る競合もあって、ぶつかり合う要素が満載だったのです。 さて、同時代の日本と中国は?
📺 西暦600年代(7世紀)の日本&中国
| 日本 | 中国 | |
| 特徴 | 西暦600年代の日本は、飛鳥時代から奈良時代手前にかけての時期です。この時代は、仏教の導入と国家体制の整備が進んだ時期です。 | 『遣隋使』の派遣先であった『隋』は内乱の末にアッサリ滅亡しました。短命に終わります。代わりに唐の時代(618年 - 907年)が始まりました。 |
| 政治 | 大化の改新(645年)は、中央集権的な国家体制への移行を促しました。朝鮮の百済が滅亡したとき、日本は百済を支援しようとしましたが、失敗しました。 | 唐の第二代皇帝太宗(李世民)は、中国史上最も有能な皇帝の一人とされ、国内の安定と発展に貢献しました。外交と貿易も、シルクロードを通じて拡大しました。 |
| 文化 | 遣隋使や遣唐使の派遣により、中国から文化や技術、文字の導入が進みました。寺院建築や仏像などが多く作られました。 | 唐は中国史上最も繁栄した時代の一つとされ、文化、経済、技術の面で大きな発展を遂げました。 |
| 社会 構造 | 天皇や摂政(聖徳太子)を中心とした、より組織的な国家体制が整備されました。中国のような律令制の導入です。 | 唐は多民族国家だったので、科挙制度を確立し、官僚の選出方法を家柄ではなく貢献度に変革しました。 |
| 宗教 | 日本初の本格的な仏教寺院である飛鳥寺が建立されました。法隆寺が建てられたのもこの頃。現存する世界最古の木造建築物。 | 中国もまた、仏教が隆盛を極め、多くの寺院が建立されました。 |
🔍 飛鳥時代の解説
 飛鳥時代とは、天皇の宮殿が奈良県明日香村に移転し、そこが政治の中心になった時代のことを指します。
飛鳥時代の初期には、蘇我馬子や聖徳太子などが有名です。
古代豪族の蘇我氏は、当時の強力な〝氏族〟の一つで、飛鳥時代に特に影響力を持っていました。彼らは朝鮮半島の百済に起源を持ち、実際この時期、百済から大量にやって来た王朝貴族たち(渡来人)は政治、文化、技術の各分野で大きな影響を与えました。
蘇我氏の母国である百済も、300年前に仏教が伝来し、国家の保護と支援の下で発展しました。
なので、百済を起源とする蘇我氏は、日本国内の仏教の導入や推進に深く関わり、聖徳太子とともに仏教政策を推進したことで知られています。
💟【日本と百済は、仲が良かった】
百済は、かつて朝鮮半島の南西部を治めていた国ですが、新羅と(中国)連合軍の圧力に、かなり力を失いました。
日本と百済は昔から仲が良く、文化や技術交流が盛んでした。そのため、660年に百済が滅びそうになったとき、王族や多くの貴族が日本へ逃げ込み(亡命)、母国への支援を求めました。
これに応えて、日本は百済を助けるために軍を送ったのですが、663年の白村江の戦いで、新羅・唐の連合軍とぶつかり合うと、地の利がなかった日本の派遣軍はアッサリ負けました。
百済の王族や貴族が日本に亡命したことは『古語拾遺 第2巻 その 5⃣』にも記録されています。
飛鳥時代とは、天皇の宮殿が奈良県明日香村に移転し、そこが政治の中心になった時代のことを指します。
飛鳥時代の初期には、蘇我馬子や聖徳太子などが有名です。
古代豪族の蘇我氏は、当時の強力な〝氏族〟の一つで、飛鳥時代に特に影響力を持っていました。彼らは朝鮮半島の百済に起源を持ち、実際この時期、百済から大量にやって来た王朝貴族たち(渡来人)は政治、文化、技術の各分野で大きな影響を与えました。
蘇我氏の母国である百済も、300年前に仏教が伝来し、国家の保護と支援の下で発展しました。
なので、百済を起源とする蘇我氏は、日本国内の仏教の導入や推進に深く関わり、聖徳太子とともに仏教政策を推進したことで知られています。
💟【日本と百済は、仲が良かった】
百済は、かつて朝鮮半島の南西部を治めていた国ですが、新羅と(中国)連合軍の圧力に、かなり力を失いました。
日本と百済は昔から仲が良く、文化や技術交流が盛んでした。そのため、660年に百済が滅びそうになったとき、王族や多くの貴族が日本へ逃げ込み(亡命)、母国への支援を求めました。
これに応えて、日本は百済を助けるために軍を送ったのですが、663年の白村江の戦いで、新羅・唐の連合軍とぶつかり合うと、地の利がなかった日本の派遣軍はアッサリ負けました。
百済の王族や貴族が日本に亡命したことは『古語拾遺 第2巻 その 5⃣』にも記録されています。
🔍 この時代の解説
西暦600年代は、日本の飛鳥時代にあたります。 飛鳥時代は、710年に平城京に首都が移るまで続き、日本が統一国家になりつつある、重要な時期でした。 この時代は、仏教の導入や国家体制の変化が目立ちます。特に、大化の改新と律令制の確立は、歴史の授業でも取り上げられるほど。 天皇は政治と宗教の両面で中心的な役割を果たし、日本国家としての基礎を築きました。 この時期の代表的な天皇とその活躍は? 🌼 推古天皇 (在位期間 592-628年) ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-日本史上初の女性天皇で、聖徳太子と共に、仏教の受容と国家体制の整備に努めました。この時代は、法隆寺などのもが建立され、仏教文化が花開きました。
🌼 舒明天皇 (在位期間 629-641年) ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-推古天皇と聖徳太子の後を継ぎ、仏教と国家を密接に結びつける政策を推進しました。仏教文化の普及が促進され、仏教が日本の社会と文化に深く根付く基盤が築かれました。
🌼 孝徳天皇 (在位期間 645-654年) ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-中大兄皇子&中臣鎌足が大化の改新(645年)を行ったときの天皇です。 蘇我氏という豪族(氏族)の強すぎる影響力を減少させ、朝廷の権力を強化しました。また、土地を国有化し、戸籍を作成、租税制度を整備することで、中央集権的な国家体制を確立しました。
🌼 天智天皇 (在位期間 668-671年) ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-即位前は中大兄皇子として知られ、即位後は大化の改新を継続しました。 国家体制の整備に力を入れ、唐に倣った律令制をがんばりました。 法律・規則、官僚制度、土地と人口に基づく税制です。
🌼 天武天皇 (在位期間 673-686年) ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-大海人皇子としても知られ、天智天皇の弟です。 飛鳥浄御原令の制定、地方行政の再編成など、国家統治の基盤を固める政策を行いました。 『日本書紀』の編纂を命じたことでも知られています。
🌼 持統天皇 (在位期間 690-697年) ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-女性天皇。 女性天皇で、天武天皇の後を継ぎました。 国内の安定と秩序の維持に努め、政治的な混乱を避けるための施策を実施しました。
 西暦700年代の日本&中国
西暦700年代の日本&中国