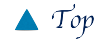🕰 西暦400年代の世の中はどんな感じ?
時は西暦400年代。 この時期は、世界史の舞台でいろいろな動きがありました。 主な出来事を見てみると? ・ ・まずは、ヨーロッパ。 西ローマ帝国は、大変なことになってます。 ゲルマン民族がドンドン押し寄せて、帝国の権威は急速に低下。内部もゴタゴタ。 とうとう476年に「終幕」となってしまいました。 一方で、東ローマ帝国(後のビザンティン帝国)の方は、サーサーン朝ペルシャと国境を巡ってちょっともめごとはありましたが、なかなか安定政権。その後もしばらく存続します。 ・ ・ そしてキリスト教。こちらはどうなったでしょう? キリスト教の影響力は、この時代に大きく広がりました。 なんといってもローマ帝国のお墨付きが大きかった! ローマ帝国を通じてどんどん広がりを見せ、ヨーロッパ中で急拡大。 後の政治や文化にまで、大きな影響を与えることとなります。 さて、同時代の日本と中国は?
📺 西暦400年代(5世紀)の日本&中国
| 日本 | 中国 | |
| 特徴 | 西暦400年代の日本は、古墳時代にあたります。 この時代の最も大きな特徴は古墳の巨大化。代表例は奈良の「仁徳天皇陵古墳」です。 | 同時代の中国では、南北朝時代の始まり。北部は遊牧民族の王朝、南部は漢民族の王朝によって統治されていました。 |
| 興亡 | 大和朝廷の影響力が東にも強化され、日本列島の統一に向けた動きが加速しました。 | 北朝では多様な民族の文化が混ざり合い、南朝では海外との交流が盛んになりました。 |
| 道具 | 朝鮮半島や中国との交流により新しい技術や文化も導入されました。 | 農業技術、製鉄技術、造船技術などが進歩しました。 |
| 文化 | この当時の古墳から『古文書』に記載の通りの剣や鏡、勾玉などが多数発見されています。 | 北朝では芸術全般が、南朝では特に文学が発展しました。 |
| 社会 構造 | 天皇配下の政治組織と社会階層が発展し、地域の豪族は力を強めました。各地の豪族は古墳を残します。 | 北魏では孝文帝による改革(等族制の実施など)が行われました。 戦乱後の農村は自給自足に傾きました。 |
| 宗教 | 古墳に埴輪が置かれるようになりました。人形や動物の形の土器です。 | 仏教が中国全土で広く受け入れられ、多くの寺院が建立されました。 |
🔍 この時代の解説
 この頃の日本は、古墳時代です。
『大和朝廷』は、近隣国の王朝と交流をしながら改革を進めていったので、この時期の日本と中国は、元々は異なる歴史的軌跡を辿りながらも、文化や技術の発展において、類似点がどんどん出てきます。
特にこの頃は、海外の貴族達が数万人単位で日本にやって来ました。
この頃の『大和朝廷』の天皇は?
🌼 仁徳天皇(在位期間 4世紀後半 - 5世紀前半)
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
この頃の日本は、古墳時代です。
『大和朝廷』は、近隣国の王朝と交流をしながら改革を進めていったので、この時期の日本と中国は、元々は異なる歴史的軌跡を辿りながらも、文化や技術の発展において、類似点がどんどん出てきます。
特にこの頃は、海外の貴族達が数万人単位で日本にやって来ました。
この頃の『大和朝廷』の天皇は?
🌼 仁徳天皇(在位期間 4世紀後半 - 5世紀前半)
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
日本最大の前方後円墳の主であると噂されているアノ人。 発掘調査は国によって禁じられているので、真相は謎ですが 現役時代は、国内統治の強化と豪族との関係構築に努めたとされます。
🌼 履中天皇(在位期間 5世紀前半) ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-『日本書紀』によると、彼は温和な性格だったとされています。 彼の時代は、古墳時代の中期にあたり、 政治的な中心地は奈良にありました。
🌼 反正天皇(在位期間 5世紀中頃) ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-20代目の天皇とされ、履中天皇の子と伝えられています。 彼の治世もまた詳細は不明ですが 『日本書紀』には彼が法を重んじ、国を治めたと記されています。
🌼 允恭天皇(在位期間 5世紀中頃) ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-一般には538年頃に仏教が朝鮮半島から伝わったとされますが 允恭天皇の時代にも、仏教が朝鮮半島から伝来し、その受容にまつわる逸話も残っています。
🌼 安康天皇(在位期間 5世紀中頃) ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-允恭天皇の子。正確な在位年代は不明。 『日本書紀』には彼の時代に起きた宮廷内の争いや 暗殺の話が記されています。
🌼 宣化天皇(在位期間 5世紀後半) ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-23代目の天皇。正確な在位年代は不明。 『日本書紀』には彼の治世に発生した地震、異常気象、疫病の流行などの記述があります。
 西暦500年代の日本&中国
西暦500年代の日本&中国