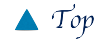🕰 『日本神話』が歴史とぶつかった日!
… 西暦200年代 … 実は、この時代は日本の歴史上、一番有名なシャーマン(霊能者)が活躍した時代でもあります。 その名は、卑弥呼。(日巫女) ヨーロッパに、神の子が現れた200年後。日本には、神の遣いの女王が現れました。 『魏志倭人伝』の中の〝邪馬台国の卑弥呼〟が、まさにこの時代の人なのです。 この西暦200年代とは、いったいどんな時代だったでしょう? この時代は、ローマ帝国、中国、インドの諸王国にとって、重要な変革期でした。 ✦ ローマ帝国この時代の初めは、セプティミウス・セウェルス帝の頃で、彼の治世は比較的安定してましたが、その後の皇帝たちはしばしば暗殺。政治的な混乱が見られ、西暦200年代の半ばには、ローマ帝国は「危機の3世紀」と呼ばれる、経済的、軍事的な困難に襲われました。
✦ 中国中国は「三国時代」 魏・蜀・呉 の三国が、中国の中で覇権を争ってました。この時代は、政治や英雄的な戦いが数多く記録されており、邪馬台国のことを語る『魏志倭人伝』とは、『三国志』の『魏志』という歴史書の中の倭人伝という章のことです。これは、この時代の日本に関する貴重な記録です。
✦ インドインドは、北はヒマラヤ山脈、南はインド洋に向かう高原や平野が広がるため、地域ごとに異なる文化や言語、宗教が発展していた土地でした。そのためこの時期は、多くの小さな王国が並立。争いが起こりました。ただ、この時代の後半は、グプタ朝が出てきます。後に「インドの黄金時代」へと繋がる変化です。
同時代の日本と中国の比較は、どんな感じだったでしょうか?📺 西暦200年代(3世紀)の日本&中国
| 日本 | 中国 | |
| 特徴 | この時代の日本は、弥生時代末期〜古墳時代の入り口にあたり『神武天皇』を起点とした、ヤマト政権がスタートしています。 | 同時期の中国は、光武帝の後漢朝の衰退と崩壊で、魏・蜀・呉 の三国に分裂した時期です。歴史小説やゲームで有名なあの時期です。 |
| 外交 | 王族が政治権力を握ると、外国からも扱いが丁重に変わるので、以降の天皇の代も、朝鮮の王族や中国王朝とのやり取りが活発に続きます。 | 三国時代の外交は、北方のモンゴル民族や中央アジアやインドの異民族とも関わりがありました。日本もです。 |
| 道具 | 王族同士の交流は、貢ぎ物を交換します。その結果、織物、土器加工物、金属工芸なども飛躍的に発展します。 | 戦国時代なので、兵器や戦術の進化が見られました。紙がより広く使われ、記録が一般的になりました。 |
| 社会 構造 | 地方豪族を『天皇家』が統合しています。天皇配下の側近も各地方の統率者になり、地方からも王政を支えます。 | 三国時代の外交政策は、戦略的な利点を優先し、軍事的にも政治的にも短期利益に重点を置く傾向がありました。 |
| 宗教 | 古墳時代の始まりは、初代天皇のために作られた大型の前方後円墳から始まります。以降、奈良の大和地方や天皇配下の豪族の地に、さまざまな古墳が作られるようになります | 中央アジアやインドとの文化的な交流で、仏教が中国に伝来し始めました。なぜか、儒教が国家の公式イデオロギーとして復興しました。 |
📺 『邪馬台国』の謎は解けるか?
日本の歴史の中で、その地を治めていた『女王の名』や『国名』は誰もが知ってるのに、肝心の場所がどこだかわからない…… という、奇妙な謎があります。 学校の歴史の授業で教わった『邪馬台国』です。 ・ ・ なぜそのような奇妙なことが起こっているかというと、この『邪馬台国』の存在は、日本のことなのに、中国の『魏志倭人伝』で初めて知ったからです。 『三国志』の『魏志』という歴史書を、後の時代の人が翻訳してみたら〝倭人伝〟という章があった。 「あれ? 日本のことが書いてある! この頃から日本と中国間に交流があったなんてビックリ!」 と、内容を見てみたら、それまで誰も知らなかった『邪馬台国』という名が、いきなり飛び出してきた。 しかも、秘術使いの女王のことまで書かれていて、ココに書かれてる邪馬台国ってどこだ?? ……というのが、日本の歴史の最大の謎になったわけです。 ・ ・ 古代日本が、この頃からすでに、国際的な外交関係を持っていたこと。 これも、とても驚く発見として、とらえられました! |
『遣隋使』や『遣唐使』ならわかります。 でもそれ以前の中国や朝鮮は、そもそも言葉通じるの? |
💻 関連LINK……『邪馬台国』の場所を特定しました!
 西暦300年代の日本&中国
西暦300年代の日本&中国