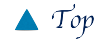🌏 歴史と『日本神話』をぶつけるとどうなる?
あれからサクッと100年経って、紀元前500年代になりました。
早いでしょ? こんな感じでサクサク進んでいきますので、この後『日本神話』が絡んでくるのをどうぞお楽しみに。
『日本神話』が絡んで来た後は、『神話』と『歴史』が一本の糸でつながって、急に面白くなりますからね!!
・
・
ここからは 紀元前500年代 の日本のお話です。
この頃の日本は、「縄文時代後期」から「弥生時代初期」へと、そろりそろりと変わり始めていた頃。
でもね、これが面白いことに、縄文と弥生って、きっちり分かれてるわけではないのです。
縄文と弥生は、だんだん混ざり合いながら、徐々に稲作文化に変わっていった。
・
・
さてさて、紀元前500年頃。
その頃、日本と中国では、違う道を歩んでました。
このタイミングで、日本では稲作技術が始まったわけですが、これ、実は偶然じゃないんですよ。両国間でリンクしてるのです。
その「大陸から稲作文化の伝来」という表現、なんか曖昧じゃないですか?
いったい誰が持ち込んだのか、それが分かれば歴史はもっと面白くなります!
実は、今まで歴史学者が見ていた世界と違って、霊能者が神話と歴史を絡めながら解説することは、切り込み方の視点が違うので、皆さんが知らない世界となります。
私の解説は、霊能力を駆使して神様に質問しながら書いてます。
一般の人にはできない、特別な手法も駆使してますので、きっと、今まで専門家にも知られていなかった予想外の事実もたくさん出てくると思います!!
・
・
縄文時代……狩りや採集で生きていた時代 弥生時代……お米を作り始めた時代
中国……春秋時代が終わりを告げ、戦国時代の幕開け 日本……稲作技術が始まった
 |
そうなんですか? でも、学校で習ったのは 「大陸から稲作文化の伝来」という言葉でしたよ! |
🔍 「大陸から稲作伝来」の理由をご存知ですか?
歴史の教科書には「大陸から稲作伝来」という表現で書かれてます。
でも、よく考えてみてください! お米や青銅器だけが偏西風に乗って
「こんにちは、ボクたち、お米と鉄器だよ!」なんて言いながら勝手に飛んできたわけではないのです。
大陸文化が日本に流れ込んだ理由…… それは何か?
中国での動乱!
・
・
歴史を見ると、どこどこの『新王朝』が『前王朝』を倒した! とか、諸侯国同士で争って『秦』が統一を果たしたとか、その一言で終わります。
そのとき、破れた方の『諸侯国』ってどうなるか知ってますか? おとなしく地方で隠居生活ではありません。
戦犯は、ピッカピカにお掃除されるのです。
力のある一族や、高級官僚を生きたまま見逃してしまうと、裏で再結集されてクーデターを起こされる危険性が残るので、力のあるグループほど、逃げても追いかけられる。
だから、「危ない! このままでは墜とされる」となった諸侯国からは、大量の「海外脱出組」が出てきます。
諸侯国の王族や高級官僚といったスーパーエリートたちほど、本気で逃げる。
上層部ほど、敗退が近づくと先手を打って「国外逃亡」するわけです。
・
・
その行き先は、朝鮮半島であったり、ベトナム方面であったり、台湾方面であったり。そして……。
海の右側に、なにやら細長い島国がありますよね? 諸侯国のスーパーエリートたちの脱出先にちょうど良さそうなリゾート地。
 この土地はその当時、縄文時代のウッホッホ族の島(推定人口70万人未満)らしい。
戦いに疲れた諸侯国の王族や高級官僚が目を向けた先、それが縄文時代の日本だったのです。
多くは朝鮮や台湾、ベトナム、モンゴル方面にも逃げたけど、最大権力の王族は、陸路ではなく、より安全な逃亡先として日本を選んだのですね。
・
・
この王族たち、ちょっと前までは中国での最大権力者たちだったわけですから、逃亡のときも質素な単独行動になんてならない。
王族が「国外逃亡」するときは、側近の高級官僚、貴族や製造業、身の回りの世話役など、大部隊のユニットを丸々抱えこんでの大移動となります。
だから、日本にやって来たのは安全への「本気度」が桁違いのスーパーエリート層。陸路で逃げた人たちよりはるかに大物ばかりが、日本にやって来てたのです。
日本の稲作文化の伝来は、それが理由なのです。知らなかったでしょ?
この土地はその当時、縄文時代のウッホッホ族の島(推定人口70万人未満)らしい。
戦いに疲れた諸侯国の王族や高級官僚が目を向けた先、それが縄文時代の日本だったのです。
多くは朝鮮や台湾、ベトナム、モンゴル方面にも逃げたけど、最大権力の王族は、陸路ではなく、より安全な逃亡先として日本を選んだのですね。
・
・
この王族たち、ちょっと前までは中国での最大権力者たちだったわけですから、逃亡のときも質素な単独行動になんてならない。
王族が「国外逃亡」するときは、側近の高級官僚、貴族や製造業、身の回りの世話役など、大部隊のユニットを丸々抱えこんでの大移動となります。
だから、日本にやって来たのは安全への「本気度」が桁違いのスーパーエリート層。陸路で逃げた人たちよりはるかに大物ばかりが、日本にやって来てたのです。
日本の稲作文化の伝来は、それが理由なのです。知らなかったでしょ?
 この土地はその当時、縄文時代のウッホッホ族の島(推定人口70万人未満)らしい。
戦いに疲れた諸侯国の王族や高級官僚が目を向けた先、それが縄文時代の日本だったのです。
多くは朝鮮や台湾、ベトナム、モンゴル方面にも逃げたけど、最大権力の王族は、陸路ではなく、より安全な逃亡先として日本を選んだのですね。
・
・
この王族たち、ちょっと前までは中国での最大権力者たちだったわけですから、逃亡のときも質素な単独行動になんてならない。
王族が「国外逃亡」するときは、側近の高級官僚、貴族や製造業、身の回りの世話役など、大部隊のユニットを丸々抱えこんでの大移動となります。
だから、日本にやって来たのは安全への「本気度」が桁違いのスーパーエリート層。陸路で逃げた人たちよりはるかに大物ばかりが、日本にやって来てたのです。
日本の稲作文化の伝来は、それが理由なのです。知らなかったでしょ?
この土地はその当時、縄文時代のウッホッホ族の島(推定人口70万人未満)らしい。
戦いに疲れた諸侯国の王族や高級官僚が目を向けた先、それが縄文時代の日本だったのです。
多くは朝鮮や台湾、ベトナム、モンゴル方面にも逃げたけど、最大権力の王族は、陸路ではなく、より安全な逃亡先として日本を選んだのですね。
・
・
この王族たち、ちょっと前までは中国での最大権力者たちだったわけですから、逃亡のときも質素な単独行動になんてならない。
王族が「国外逃亡」するときは、側近の高級官僚、貴族や製造業、身の回りの世話役など、大部隊のユニットを丸々抱えこんでの大移動となります。
だから、日本にやって来たのは安全への「本気度」が桁違いのスーパーエリート層。陸路で逃げた人たちよりはるかに大物ばかりが、日本にやって来てたのです。
日本の稲作文化の伝来は、それが理由なのです。知らなかったでしょ?
📺 紀元前500年代の日本&中国
| 日本 | 中国 | |
| 特徴 | 紀元前500年頃の日本は、縄文時代後期から弥生時代初期にかけての時期です。この時期に彼らがやって来ました。 | 同じ時期の中国は、春秋時代の終わり頃。諸侯たちがたんだん偉ぶってきて、お互いに権力争いを始めました。 |
| 争い ・ 交易 | 朝鮮半島や中国との交易が活発になり、文化や技術の交流が進みました。 (エリート達の本国とのやりとり) | 多くの諸侯国が争い、勢力を拡大しようとしていました。鉄製武器なども登場。負けた諸侯たちは、国外に逃げました。 |
| 道具 | 縄文時代の土器から弥生時代の土器へと変化が見られ、稲作に適した形状になりました。 | 鉄器の使用が普及し、農業や軍事技術に大きな変化をもたらしました。 |
| 文化 発展 | 埋葬方法に変化が見られ、墓の大型化が始まりました。 (旧王族たちの墓なので、豪華) | 儒教の創始者である孔子が生まれました。『論語』のあの人です。その後も多様な思想が競い合う「百家争鳴」の時代でした。 |
| 農業 技術 | 先の理由で大陸から稲作が伝わったので、農業が徐々に普及してきました。 | 鉄器の使用がより進みました。土地の使用も、より大きくなりました。 |
| 社会 構造 | 先の理由で、定住する集落が形成され、社会構造が徐々に変化し始めました。集落単位で社会組織が形成され、地域間のネットワークが発展し始めました。 | 多くの都市が成長し、商業や手工業が発展しました。貴族中心の社会から、より多様な階層社会へと変わりつつありました。 |
| 文字 | 外国からの一派は、個人としては読み書きできました。ただ、国家レベルでの文字使用となると、まだまだ先です。 | この時期には既に漢字が使われており、文化や行政の発展に寄与していました。 |
🔍 「国外逃亡」した王族達のその後
彼らは、日本に着いたらそこで終わりではありません。
翌日からは、逃亡先での新たな生活が始まります。
食べ物が確保できなかったら、生きていけない。
新たな土地では『開拓者』として生活の基盤を整えなければいけないので、現地の人には積極的に稲作技術を教えました。農作業用の鉄器の使用も教えました。
・
・
侵略ではなく、新たな土地で共存共栄を図るために、王族達はそうやって、質素ながらも生き延びる道を選んだのです。
日本に流れ着いた部隊は一つだけではありません。
争いのたびに「国外逃亡」のエリート達は出てくるわけですから、断続的に第2波、第3波… と続きます。
彼らが最初に選んだ日本の土地は、考古学的な発掘から、だいたい特定されています……
初期は、西日本が中心。
・
・
これが、大陸文化が日本に流れ込んだ理由なのです。
よく「渡来人」と一言でくくられますが、日本に来た彼らは、どこにでもいる一般人とは違います。
中国の中でも上位1%のスーパーエリート。
一般人に、大規模な船団なんて用意できませんし、そもそも一般人が、自分たちの国を捨てて、わざわざ移住してくる理由もない。
日本に来た彼らは、逃げてきた〝王族級〟の人たちばかりだった。
それも、大規模な船団を用意して、周辺の貴族や技術者たちまでまとめて引き連れてこれるような王族たちだったわけですから、当時の日本の人口(70万人未満)に対してその影響はとても大きかった。
日本の縄文時代の人たちが、部落で暮らしているところに、これらのエリート集団が大量に降りてきたものだから、彼らがそのまま『地方豪族』におさまったわけです。
こうして、弥生時代の階級社会が始まる。
ほら、歴史ってつながってるでしょう?
真実は一つなのです。だから、その真実に気がつくと、歴史の中のいろんな事実が、一本の糸でつじつまが合ってくるのですよ。
 紀元前400年代の日本&中国
紀元前400年代の日本&中国
| 説明 | |
| 出雲
地方 |
現在の島根県(出雲)は、弥生時代から稲作が盛んで、豊かな自然環境と良好な水利条件でした。この地域の稲作技術は高度で大規模な水田だったことが、発掘で知られています。 |
| 九州 地方 | 現在の福岡県(筑前)、大分県(豊後)、北部九州(豊前)は稲作の導入が早く、弥生時代から重要な稲作地域でした。 |
| 山 陽 道 | 現在の兵庫県(播磨)や岡山県(備前)は、瀬戸内海に面し、温暖な気候で稲作に適していました。播磨地方も、大規模な集落跡が見つかってます。 |
| 東 海 道 | 現在の愛知県(尾張、三河)や静岡県(遠江)は、温暖な気候と肥沃な土地を持ち、稲作が盛んでした。特に三河地方は、弥生時代の大規模な水田跡が発見されています。 |
 紀元前400年代の日本&中国
紀元前400年代の日本&中国