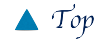🕰 西暦300年代の世の中はどんな感じ?
西暦300年代、世界の多くの地域では、重要な変化が起こっていました。
同時代の主な出来事や状況は?
✦ ローマ帝国
まずはヨーロッパの最大勢力のローマ帝国です。
その頃は帝国の改革が進行中。帝国を東西分割して、四帝支配体制にすることで、広大な領土をうまくまとめようとしてました。
✦ 続いて、キリスト教のお話。
この頃キリスト教は、弾圧を乗り越えてじわじわとローマ帝国内に広がっていました。この流れがついに、コンスタンティヌス大帝による公認につながり、その後のキリスト教の大躍進につながります。
✦ サーサーン朝ペルシャ
ヨーロッパの東方に目を向けると、サーサーン朝ペルシャが、強大な勢力を誇ってました。
東ローマ帝国とは、しばしば紛争がおこっていました。
✦ 最後に、シルクロード。
シルクロードは、東西の国々を結ぶ交易路なので、ここを通じて国際的な商業活動が行われてました。
中国からは、絹やスパイスなどが輸出され、ローマからはガラス製品や宝石などが中国へ。
その真ん中のサーサーン朝ペルシャは、東西の交易の双方から利益を得られたことで、一気に強国になったのです。
さて、同時代の日本と中国は?
📺 西暦300年代(4世紀)の日本&中国
| |
日本 |
中国 |
| 特徴 |
西暦300年代の日本は古墳時代。ヤマト政権が西日本の広範囲を支配下に置き、統一国家の形を強めました。奈良の地には、ヤマト政権の権力者たちの古墳が多数建築され、各地にも配下の豪族の古墳が建造されました。 |
中国では、三国時代の後、晋が一時的に国を統一したものの、内乱と北部のモンゴル系民族の侵入により、再び分裂。北部では非漢民族の十六国が興亡を繰り返し、中国は南北に分裂しました。南北朝時代です。 |
| 交易 |
ヤマト政権が国家形成に向けて動いていました。対外的に見ても、ヤマト政権によって朝鮮半島や中国との交易が盛んになり、文化や技術の交流が活発になりました。 |
様々な民族が北部でごった煮状態になりました。ただ、そのおかげで、モンゴル系他民族との文化的な交流が進みました。シルクロードを通じた東西交易も盛んでした。 |
| 道具 |
技術が大きく進歩し、特に鉄製品の製造が目立ちました。農業の効率化に役立つ鉄製農具や、戦闘用の武器が社会発展と軍事力強化に寄与しました。また、古墳時代特有の、あの埴輪が登場します。 |
鉄製の農具や武器の製造が進展し、特に北方の民族は騎馬戦に適した武器や装備を開発していました。また、陶磁器の技術も向上し、美しい陶器が作られていました。 |
| 社会
構造 |
ヤマト政権の後継皇族と有力貴族が地方を支配し、中央集権的な国家体制に移行していました。同時多発的に古墳が生まれた理由は、地域の豪族が天皇系列の支配下だったからです。 |
北部ではモンゴル系民族との軍事的な衝突が多く、多くの民衆が苦しみました。その混乱で経済と文化の中心は南に移動しました。農村部では自給自足の傾向が強まりました。 |
| 宗教 |
「秦の王族」の子孫グループが、秦の始皇帝陵に倣って、大型の古墳を次々と作ります。 |
中国では、仏教が北方の民族国家を中心に広まり、南北朝時代には南方でも広く受け入れられました。道教も人気があり、民間信仰と結びつきながら発展しました。 |
🔍 この時代の解説
西暦190年あたりに奈良の橿原で『ヤマト政権』が誕生し、西日本一帯を統一することに成功しました。
なぜ、西日本だけだったのか? 東日本は? というと、愛知から先の進路をふさぐように、奥羽山脈と伊豆&箱根の山々が壁を作って邪魔してたからです。
 山から先は半分『外国』扱いだったのです。
ヤマト政権は、他の地域豪族を支配下に置き、有力な地域には直接役員を派遣しました。これにより、天皇配下の側近が地方の統率者として据えられ、強力な中央集権化が進められました。
初代天皇の時代から約100年、200年が経過すると、中国や朝鮮半島との交流が進み、権力基盤が整いました。
このあたりから、天皇&側近たちによる中央集権的な国家体制がさらに強化され『天皇政治』としての体制が確立しました。
そしてこの時代、西暦300年代あたりから、『大和朝廷』と呼ばれるようになりました。
山から先は半分『外国』扱いだったのです。
ヤマト政権は、他の地域豪族を支配下に置き、有力な地域には直接役員を派遣しました。これにより、天皇配下の側近が地方の統率者として据えられ、強力な中央集権化が進められました。
初代天皇の時代から約100年、200年が経過すると、中国や朝鮮半島との交流が進み、権力基盤が整いました。
このあたりから、天皇&側近たちによる中央集権的な国家体制がさらに強化され『天皇政治』としての体制が確立しました。
そしてこの時代、西暦300年代あたりから、『大和朝廷』と呼ばれるようになりました。
 西暦400年代の日本&中国
西暦400年代の日本&中国
 山から先は半分『外国』扱いだったのです。
ヤマト政権は、他の地域豪族を支配下に置き、有力な地域には直接役員を派遣しました。これにより、天皇配下の側近が地方の統率者として据えられ、強力な中央集権化が進められました。
初代天皇の時代から約100年、200年が経過すると、中国や朝鮮半島との交流が進み、権力基盤が整いました。
このあたりから、天皇&側近たちによる中央集権的な国家体制がさらに強化され『天皇政治』としての体制が確立しました。
そしてこの時代、西暦300年代あたりから、『大和朝廷』と呼ばれるようになりました。
山から先は半分『外国』扱いだったのです。
ヤマト政権は、他の地域豪族を支配下に置き、有力な地域には直接役員を派遣しました。これにより、天皇配下の側近が地方の統率者として据えられ、強力な中央集権化が進められました。
初代天皇の時代から約100年、200年が経過すると、中国や朝鮮半島との交流が進み、権力基盤が整いました。
このあたりから、天皇&側近たちによる中央集権的な国家体制がさらに強化され『天皇政治』としての体制が確立しました。
そしてこの時代、西暦300年代あたりから、『大和朝廷』と呼ばれるようになりました。
 西暦400年代の日本&中国
西暦400年代の日本&中国