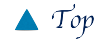🌏 歴史と『日本神話』をぶつけるとどうなる?
ここからは 紀元前300年代 のお話です。
紀元前300年頃、海の向こうの中国の地は、まるで日本の〝安土桃山時代〟のような、バチバチの戦国時代。
 戦国七雄(秦、韓、魏、趙、燕、楚、斉)と呼ばれる強国がバトルロワイヤルを繰り広げる中、その中で少しずつ「秦」が周りを倒し始め、後の中国統一への道を進み始めていました。
一方、日本の方は?
こちらは羊の牧場。平和そのもの。
中国本土の戦乱を嫌って、黄金の国ジパングに逃亡してきたエリート族も、日本の地では平和な民。
元々は支配層だったために、日本に来た後も地方集落の上層部になってはいるものの、圧政や殺戮という感じではなく、争いよりも共存共栄をはかっていた。
結果的に、最高レベルのエリートたちだけがやって来たことが、日本の平均点を押し上げ、国力UPのキッカケになったのです。
戦国七雄(秦、韓、魏、趙、燕、楚、斉)と呼ばれる強国がバトルロワイヤルを繰り広げる中、その中で少しずつ「秦」が周りを倒し始め、後の中国統一への道を進み始めていました。
一方、日本の方は?
こちらは羊の牧場。平和そのもの。
中国本土の戦乱を嫌って、黄金の国ジパングに逃亡してきたエリート族も、日本の地では平和な民。
元々は支配層だったために、日本に来た後も地方集落の上層部になってはいるものの、圧政や殺戮という感じではなく、争いよりも共存共栄をはかっていた。
結果的に、最高レベルのエリートたちだけがやって来たことが、日本の平均点を押し上げ、国力UPのキッカケになったのです。
 戦国七雄(秦、韓、魏、趙、燕、楚、斉)と呼ばれる強国がバトルロワイヤルを繰り広げる中、その中で少しずつ「秦」が周りを倒し始め、後の中国統一への道を進み始めていました。
一方、日本の方は?
こちらは羊の牧場。平和そのもの。
中国本土の戦乱を嫌って、黄金の国ジパングに逃亡してきたエリート族も、日本の地では平和な民。
元々は支配層だったために、日本に来た後も地方集落の上層部になってはいるものの、圧政や殺戮という感じではなく、争いよりも共存共栄をはかっていた。
結果的に、最高レベルのエリートたちだけがやって来たことが、日本の平均点を押し上げ、国力UPのキッカケになったのです。
戦国七雄(秦、韓、魏、趙、燕、楚、斉)と呼ばれる強国がバトルロワイヤルを繰り広げる中、その中で少しずつ「秦」が周りを倒し始め、後の中国統一への道を進み始めていました。
一方、日本の方は?
こちらは羊の牧場。平和そのもの。
中国本土の戦乱を嫌って、黄金の国ジパングに逃亡してきたエリート族も、日本の地では平和な民。
元々は支配層だったために、日本に来た後も地方集落の上層部になってはいるものの、圧政や殺戮という感じではなく、争いよりも共存共栄をはかっていた。
結果的に、最高レベルのエリートたちだけがやって来たことが、日本の平均点を押し上げ、国力UPのキッカケになったのです。
📺 紀元前300年代の日本&中国
| 日本 | 中国 | |
| 特徴 | 紀元前300年頃の日本は、弥生時代にあたります。この時期の日本も、外国からの流入が続き、各地方に稲作文化が広がります。 | 紀元前300年頃の中国は戦国時代。七強国(秦、韓、魏、趙、燕、楚、斉)が、お互いつぶし合ってました。その中で、秦がやや優勢。 |
| 道具 | 青銅器や鉄器の使用が増え、国力を増してきました。中国から遅れること200年。農業や軍事技術にも変化が出てきました。 | 戦車や鉄製武器の騎兵部隊、『孫子の兵法』を応用した、同盟や裏切り戦術など、軍事技術が進展しました。 |
| 社会 構造 | 稲作農業が普及したことで、定住する集落が大きくなり、社会構造が階層化しています。豪族の子孫が権力を増大させてきました。 | 多くの都市が成長し、商業や手工業が発展していました。諸侯国では、法家の思想の影響から、法律が整備されました。 |
| 宗教 | 大型の墓。これは、彼らの権力の大きさでもありました。まだ古墳ではないよ。 | この時期は、儒家、道家、法家、墨家など、さまざまな学派が登場し、それぞれの思想が社会に影響を与えました。 |
🔍 この時代の日本&中国の解説
『内部抗争』は国力を分割させ、停滞させます。
中国が宿屋で一休みしている間、日本は少しずつ国力を高め始めてきました。
特に鉄製の器具の使いこなしによって、農業の効率は高まりました。耕地面積が増えたことで、稲作以外にも、粟、綿花などにも手を出し始めます。
日本に来た人たちは敗退王朝とはいえ、海路で本気で逃げるような〝王族級〟の人たちばかり。中国の中でも上位1%のスーパーエリートばかりが日本に来たので、彼らの指導を受けた日本人は、少しずつ目覚め始めました。
まだヨチヨチ歩きではあるモノの、のちの『黄金の国ジパング』あるいは『大日本帝国』に向けて、少しずつ道を進み始めました。
この時期から国力を高め始めた日本は、あれだけリードを許していた中国に少しずつ追いつき『日清戦争』のときには、武力で正面から中国を破りますからね。
日本は強かった!!
 紀元前200年代の日本&中国
紀元前200年代の日本&中国
 紀元前200年代の日本&中国
紀元前200年代の日本&中国