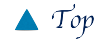📓 『カタカムナ』 全80首の意味−第53句の解説
『カタカムナ』第53句 今回は『巫女』のお話です。 古代の日本の地方政治は、なんでもかんでも『巫女』頼みでした。 雨が降ったら『巫女』に天意を質問させ、雨が降らなくても『巫女』に天意を質問させ、雷が鳴ったら、火山が噴火したら、地震が来たら、作物が病気で全滅したら…… このHPでは、カタカムナの解説を通して、日本の歴史を今までと違う切り口で明らかにしていますが、今回は皆さんの知らないお話です。 ・ ・
『カタカムナ』第53句の解説
📓 【原文】
【漢字に直すと?】『カタカムナ』 第53首
イキココロ アマナヘサカル モモヒクニ ヘツナギサヒコ ヘツカヒヘラ
『カタカムナ』 第53首🔎 【この句の意味は?】息ココロ 天名へ盛る 百日国 別渚彦 別遣い箆
『カタカムナ』 第53首『神の名』がたくさん天から降ろされた 日の本の御国… その意味するモノは? 高天原からの渡し船(巫女へのお告げ)が 天と地を行き来して… 天意を 皇倭(おおやまと)の人々が しっかり受け取れている
ひこ【皇倭って何?】
古代の日本は、【ヤマト国】と呼ばれてました。 ヤマトといえば、普通は『大和』と書く。 でもこの漢字、よく見てみると、どこをどう読んでも『ヤマト』とは読めないのですよ。完全な当て字。 ところで… 大きな和…… どこかで心当たりありません? 聖徳太子の『和をもって尊しとなす』
実際には『大和朝廷』は、古墳時代の『天皇政治』からスタートしていたので、聖徳太子の登場の前からこの言葉はあったわけですが、『大和朝廷』が重視していたものを聖徳太子が引き継いで、言語化したのが…… 『和をもって尊しとなす』 ちなみに『大和朝廷』以前の〝ヤマト〟の文字は『倭』が正解。 ・ ・ ただこの文字も本当は中国側の表記なのです。 元ネタは、中国の三国史『魏志倭人伝』の、あの『倭』から来ています。 なので、古文書にはこの字で『ヤマト』と読ませてはいるものの、実際のニュアンスは違う。 元々日本の土地で呼ばれていた『ヤマト』の語源は〝ひとかたまりの集落〟という意味の『山徒』から来ているのです。 (特定の国名を指すのではなく〝集落〟という意味で〝ヤマト〟という言葉が使われていた) 『魏志倭人伝』の記述は、弥生時代の邪馬台国のことでしたから、あの頃はまだ、日本に文字はなかったのです。 だから、言葉として『ヤマト』と発音していたものに対して、中国視察団が、勝手にあの字をあてたのです。
邪馬台国の卑弥呼に代表されるように、古代日本にはシャーマンがいました。
『別渚彦』とは? 高天原からの渡し船の案内人
今回の『カタカムナ』の句では、『別渚彦』という言葉で出てきますが、
『渚彦』……漁に出る海の男 『別渚彦』……離島への渡し船の案内人今回の『カタカムナ』で出てくる『別渚彦』とは、高天原からの渡し船の案内人。 『神のお告げ』を伝える巫女(シャーマン)のことを言っています。 ・ ・ 古代の日本の地方政治は、なんでもかんでも『巫女』頼りだったのです。 雨が降ったら『巫女』に天意を質問させ、雨が降らなくても『巫女』に天意を質問させ、雷が鳴ったら、火山が噴火したら、地震が来たら、作物が病気で全滅したら…… 政治に関連することから、天気のこと、健康のことまで、なんでもかんでも『巫女』頼み。 権力者は、『巫女』を通してしょっちゅう神様とやり取りしていた。 だから、この頃の日本は『天意』がそのまま権力者へスッと通り、『渡し船の案内人』の受け取った『神のお告げ』は、地域集落内で徹底された。 これが、昔の日本人が二言目には『かんながら…』と口癖にしていた理由で、 『神様がいる、いない』といった議論ではなく 誰にとっても、子供の頃から神様とともいる。そういう環境だったわけです。『カタカムナ』 全80首の意味−第54句の解説