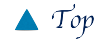📓 『カタカムナ』 全80首の意味−第46句の解説
『カタカムナ』第46句の訳です -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 今回の句は、以前に出てきた句の『伏線回収』の扱いとなります。 『カタカムナ』第4句 の解説覚えてますか? 『カタカムナ』第4句は、不自然なほど『5』という数字が好きでしたが、それは 神様が人間相手に出した『謎解き』ゲームでした! その『謎の解答』がこちらです。 『カタカムナ』第4句で出した謎を、今回の『カタカムナ』第46句で伏線回収に来ているのですが、これ…… 公開しちゃっていいのかな? セミナー等で直接会った人にしか教えてはいけないような、『秘匿レベル』が高そうな内容なのですが、もし公開するとしても『有料枠』で対象を限定して? ・ ・
『カタカムナ』 全80首の意味−第46句の解説
📓 【原文】
【漢字に直すと?】『カタカムナ』 第46首
カムナガラ…… クニカツギ フトマニノ アヤ カムナホビ オホ カムナホビ イツノメニ オホトヂムスビ イツノメノ ソコツ ワタツミ ソコツツヲ イシマトマリメグル ナカツツヲ
『カタカムナ』 第46首 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-🔎 【この句の意味は?】惟 神…… 国担ぎ 太占の術 神名祝び 大神名祝び 5ノ目に 尾ほ閉ぢ結び 5ノ目の 底つ 綿摘み(収穫) 底筒を 意思纏まり巡る 中筒を
『カタカムナ』 第46首 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-・ ・神がおっしゃるには… 国担ぎ(地方政治の進め方)のための 太占の秘術は? 神の名を謡い舞い 天照大神の名を謡い舞い…… 5つ目に 尾を閉じて結ぶ その方法が 願望成就の正式な秘法 この秘法はたちまち 地上から天に向けて光の柱を登らせ 願いが天の神々 四方八方に届く 先の正式な秘法の『願い』そのものが
この句の内容は、古代日本の【祈祷師の秘法】の解説でした。 時代としては、弥生時代〜古墳時代にかけて。 この頃の日本は、まだ『中央集権国家』ではなく、地方集落がそれぞれ国として点在していて、地方政治はその地域の支配者(豪族)によって行われていました。 農業も、工業(土器や手芸品など)も、人々に職業選択の自由など存在せず、田畑は個人所有ではなく、支配者所有の工場に出入りする労働者状態。 支配者の号令ひとつで、地域一帯で作付けをし、また支配者の号令で、集落総出で一気に摘み取る。 (収穫の時の方が派手なイベント。子供まで総出の人海戦術) これらのタイミングが適切でないと、その集落一帯のシーズンは失敗に終わる。だからこの政治判断は何よりも重要で、一人の支配者の個人判断のレベルを大きく超えていた。
【祈祷師の秘法】と『かんながらの精神』の始まり
その判断は、集落一帯に責任が及ぶ。 個人の勘や経験で行えるレベルではない。そこで出てきたのが、支配者へのアドバイス役となる【祈祷師】(シャーマン)。 その地域一帯に責任が及ぶ重要な判断であればあるほど…… 【支配者の心の内側】判断を間違えたくない ⇢ できることなら『正しい答え』を知りたい ⇢ 『正しい答え』を知る方法はないか?その思考の先に行き着くのは、昔も今も変わらないわけです。 『神頼み』 古代日本では【祈祷師】(シャーマン)が『神の遣い』と呼ばれ、模範解答を『神のご神託』として受けとっていた。 そうなれば、国担ぎ(地方政治)も安心! その地域は、正しい政治で発展できる。 それは、他の集落も同じ。 それぞれの地域ごとに、独自の『神の遣い』をたてて、神意を聞こうとした。ただ…… シャーマンの能力も、当然ながら、ピンからキリまで大きな開きがある。 いくら古代日本とはいえ、スゴイ人なんて全国中 探し回ってもわずか数人。 『卑弥呼』のような、歴史に名を残すほどのシャーマンもいれば、その集落内に他に適任がおらず、普通の人なのに任命されてしまった『なんちゃって占い師』も……。 ・ ・ 『卑弥呼』のような 能力が最高レベルのシャーマン であれば、神様(多言主)と直接会話ができ、『神のご神託』が降りてくる。 そのような国は、『邪馬台国』のようにどんどん力を増大させ、国が発展する。 しかし、そこまでの能力者となると、いくら古代日本でも滅多にいなかったので、レベルが高いシャーマンを抱えられなかった地方国は、一言主までしかアクセスできなかったり、それすら無理な場合は、かわりに太占という占いで、なんとか神意を聞き出そうとしていた。 どこの集落でも、地方政治の支配者は、神様に頼りまくりながら政治を行っていたのです。 だから、この頃の日本人にとって、「神様はいるか、いないか?」という質問は、そもそも愚問。 答えは誰にとっても明快。 どの集落も、神様に頼りながら政治が行われ、ご神託にしろ、占いの結果にしろ、その内容はすぐに『神の意志はこうだ!』と皆に周知徹底されていたのですから 古代の日本人にとっての神様は、『遠い世界にいる存在』ではなく、何かあったらすぐ目の前に出てきて、私たちを助けてくれる存在だったのです。私たちは常に、神様とともにいる…… お天道様が見てるから、私たち、悪いことデキナイね!『かんながらの精神』 の始まりです。 ・ ・古代日本の霊能者が、政治を占う正式な祈祷のときに使ってた技。 残念ながら、すでに継承は途絶えてしまい、現代では誰も知らない秘術。 神話の伝説の中でしか見ることがデキナイ技。 続いて、奈良、平安期に流行した『575形式』の和歌ですが、これは一般の認識では『貴族の教養』ということになってます。 実際、平安期には貴族同士で『お題』というものがあって、一つのテーマに対して皆が和歌を詠み合ったり、『和歌その1』の相手サーブを『返歌』のレシーブで打ち負かすという、マウントの取り合い合戦も行われていた。 しかし、元々和歌の原型は、神様から降りてきていたのです。 次のような名前で呼ばれてる神様がいます。
【祈祷師の秘法】の解説
一言主……答えしか言わない。解説ナシ。一方通行。 多言主……教師系。解説あり。双方向コミュニケーション可能。昔のシャーマンは、一言主としかコンタクトがとれないケースが多かった。 質問に対しては、ワンセンテンス型の返答。素っ気ない。 答えだけ言って、サッサと帰ってしまう。 そして、その答え方が…… 『5文字』 だったのです。(5・7調の和歌のケースもある)国担ぎ 太占の術 神名祝び 大神名祝び 5ノ目に 尾ほ閉ぢ結び 5ノ目の 底つ 綿摘み(収穫)一言主の答えは、基本『5文字』で降りてくる。 だから降ろされた方は、「神意は何か?」とヒーヒー言いながら高官同士で解釈し合う。 『和歌』の原型は、ここから来ているのです。自然発生ではない。 神様の答えが、『5音・7音』の組み合わせで、詩の形で降りてくることも多いから、その神様&質問者のやり取りに倣って、和歌の形も、短い文に深い意味を込める形が流行った。 ・ ・ 実は、日本人の伝統のいくつかも、元々は神様と巫女(シャーマン)の会話形式が原型だったものも多く『太閤』と称すもの、またの名を『木下藤吉郎』あるいは『羽柴秀吉』と申しまして、その正体は『関白』となられた『豊臣秀吉』公であり……みたいな、ワケの分からない紹介のされ方をするのも、元々は神様と巫女(シャーマン)の会話内容が、まさにそんな感じだったのです。『大国主神』は『多言主神』でもあり、『多言教神』でもある神様自らがそう名乗ってる。『カタカムナ』を訳すと本当にそう言ってる。 つまり、神様の名は『部長』とか『キャプテン』とか『赤木サン』とか『ゴリ』(学生時代のアダ名)とか、 一人の赤木さんに対して、それぞれの立場からいろいろな呼び名があるように、一人の神様も会話相手の巫女(シャーマン)に対して、その時々で、いろいろな名で名乗る。そんな感じだったのです。 だから、一人の神様がいくつもの名前で呼ばれるという、あんな面倒なことになってたわけです。
【一言主の答え方】の解説
一言主……答えしか言わない。解説ナシ。一方通行。 多言主……教師系。解説あり。双方向コミュニケーション可能。『少ない言葉で、できるだけ多くの意図を伝える』というのが、一言主の答え方だった。 だから、解釈者には教養の高さが求められる。 例えば、私が「神様、私は神様の期待通りのコトができているでしょうか?」 みたいな質問をしたとしましょう。 すると神様の答えは、和歌っぽい感じで、 『道長けども 我が意を得たり』・ その道は長いがイイ感じでやってくれてる ・ 藤原道長の件はよく見抜いたなみたいな二つの意味を持つ、短い返答を返してくる。 実際コレ、試しに今降ろしてもらったものです。 降りてきた言葉をここからどう解釈するか? それを、巫女から伝えられた権力者や高官たちがヒーヒー言いながら神意を考える。 (私の場合は、答えも同時に教わったけど。どうせ自力では解けないと思われて) ・ ・ 例えば、権力者が「神様、私は神様の期待通りのコトができているでしょうか?」とさっきと同じ質問をしたとする。 『山崩れたり 谷の山』 みたいな答えが降りてくると、おおいにビビる。 巫女自身はその意味がわからないので、その通りに権力者に伝える。 権力者と高官たちはヒーヒー言いながら意味を考える。 やがて、今の意味は…… 山とは自分の権力を指し、それが総崩れになって、最悪の結果が次々と起こるということを指すのでは? と正解に行き着き、ではどうすれば? という別な日の問いにまた…… 『人 天照し 人写し』 統率者の政治が、天のように、全ての人を助けるつもりで地域全体を光で照らす人になれ みたいに、正しい解釈が必要となる。 このような、暗号の形で降ろしてくるのが神様。 ・ ・ 『カタカムナの原文』もそんな感じだったのですよ。 だから、詩の形で示されているのです。 そして、私自身が霊能力で神様に答えを聞きながら訳しているとき、『口述筆記』みたいにラクできる機会は滅多になく、ほとんどの句が『ヒント』の形でしか降りてこないのも同じ理由。 だから、シャーマンの霊能力という『チート技』を使っているにもかかわらず、ヒーヒー言いながら訳しているわけで、ズルをしている私ですらこれですから、 何の霊能力も持たない一般の学者や研究者が『カタカムナの原文』を訳すのは、そもそも不可能だと思います!『カタカムナ』 全80首の意味−第47句の解説