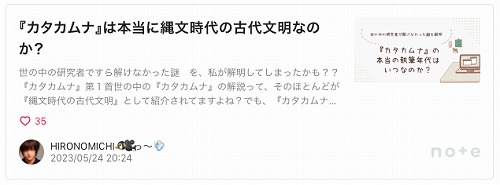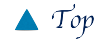📓 『カタカムナ』 全80首の意味−第17句の解説
今回は『カタカムナ』 第17句 の解説です。
この 『かんながら…』 という言葉、覚えておいてくださいね。 ・ ・ この言葉は、昔の日本では『心のお守り』として常に意識され、昔の日本人なら、誰もが知ってる言葉でした。 たとえば、奈良時代の【万葉集】を見ると、当時の人のモノの考え方が分かります。『カタカムナ』という単語は、元々は 『型』+『神名』を組み合わせた造語で、 『型』 とは 『かんながらの作法』 『神名』 とは 『神様の名前の由来』 を指しています。
【万葉集】 3253番歌 (遣唐使の出発を見送る側の歌)現代日本でも、わざわざ言葉で言わなくても『空気を読んで察する』という習慣がありますよね? これは、普通の人からは『現代人のマナー』と思われてますが、本当は古来からあった 『かんながらの精神』 の名残りなのです。 昔の人は、もっと口に出さなかった。 (必要以上のおしゃべりは、下品と考えられていた。静かさこそ、品があると) ちなみに今回はなぜ、この【万葉集】を紹介したか? というと、〝万葉集〟は奈良時代なので、原文の響きが近いからです。 そしてもう一つ…… 『カタカムナ』も第17首以降は『カムナガラ』という言葉が多発してるからです。 『カタカムナ』は今回の第17句以降、この『カムナガラ…』という言葉が、不自然なほど連発されるのです! それでは、第17句の訳に進みましょう! ・ ・
葦原の 瑞穂の国は かむながら 言挙げせぬ 国 しかれども 言挙げぞ 我がする 事幸くま 幸くませと
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・- 【現代語訳】葦原の瑞穂の国(日本のこと)は、「神の作法」にならって たとえ心の中では、嵐のように心配してたとしても 心に秘めて、言葉には出さない。そのようなつつましい国だ。 けれど、私は言葉に出して、あえて言わせていただく。 「どうぞご無事で神に守られますように!」
カタカムナ第17句の訳
📓 【原文】
【漢字に直すと?】『カタカムナ』 第17首
カムナガラ…… トヨヒカミ アマウツシ ヤホトヨノ ユツ イキ フタ ネ フタ ハシ ウキフツミ タカマカ カヅ ムスヒヌシ カタカムナ マカハコクニ ノ ヒトツ カタツミ
『カタカムナ』 第17首 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-かんながら…… 遠い神 天写し 八百(かなりという意味) 遠の言つ 息 次 願 次 橋 浮き船摘み 高天原 数々 結び主 カタカムナ 真 箱国の 人つ 型積み
 |
んんっ…? これ、なんて言ってるんですか? 私、『かんながら』しか分からなかった…… |
 カタカムナ第17句の訳
カタカムナ第17句の訳
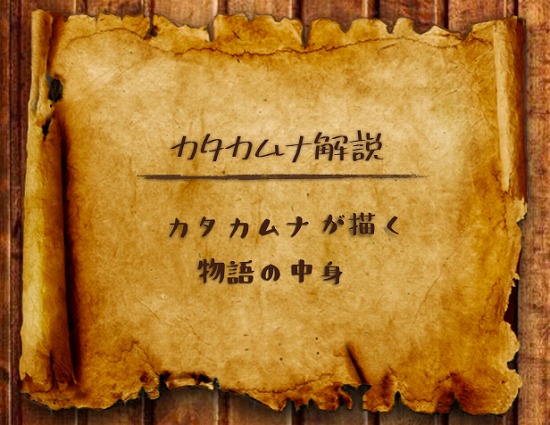 【漢字に直すと?】
【漢字に直すと?】
惟 神…… 遠い神 天写し 八百(かなりという意味) 遠の言つ 息 次 根 次 橋 浮き船摘み 高天原 数々 結び主 カタカムナ 真箱国の 人つ 型積み
神の伝えることは……? 神の姿と、地上の人間の姿は似てはいる。だが、 ただ神に願うだけでは、神は人間を助けない。 高天原の八百万の神々は、こう教えてくれている 【願いを叶える方法】として大事な順は、何か? 『息』(声に出して発音)次に『根』 そしてここからが大事なことだが 『橋』を架けて 天の神とつながる 方法…… それは? 心と身体の穢れを摘みとること (禊ぎをする) ↪ 『浮き船摘み』とは、岩場の貝獲り船 (ここでは、「身の穢れ削り」の比喩表現) 高天原の八百万の神々とつながる方法 それは、『カタカムナ』で示した作法! 高天原(真の箱国)の 神々の作法 と同じように 神が人に教えた『かんながらの道の作法』を積み上げ、人間側から神に近づくのだ。
 『口述筆記』の句には、何かがある?
『口述筆記』の句には、何かがある?
実は今回の句の訳も、自力だけではどうにもならなかったので、神様の言葉の『口述筆記』の技に頼りました。
毎回頼ってはいるのですが、気まぐれで、ヒントしか教えてくれないときもあれば、全部教えてくれるときもあって、今回はたまたま、わりとサクサク教えてもらえたバージョン。
なので、今回の訳の中には【原文にない補足解説】がいくつか見られます。
・
・
実は、最近気づいたことがあって……
どうも、神様の言葉の『口述筆記』状態でヒントが降りてくるものほど、神様からアナタに直接伝えたいコトがあるのが、だんだん分かってきました。
今まで、条件発生はランダム(神様の気まぐれ)だと思ってましたが、どうも何か大事な要素がある句のときほど、神様が『口述筆記』状態でいろいろ教えてくれる。
つまりこの句は、そのような大事な要素がある句!!
ほかにも関連の話をいろいろ教わったので、ここからはその教わったことをまとめます。
・
・
 神様がアナタに強く伝えたいメッセージ!
神様がアナタに強く伝えたいメッセージ!
今回の句で初めて『カムナガラ…』という言葉が登場しました。
【万葉集】の方にも、同じ言葉がありましたが、この時代の人は、人と神様の距離が近かったのです。
『惟神の道』の精神
それは、古代日本の『そこで暮らす人々』にとっては日常だった。
そして、『カタカムナ』の中では 【禊ぎ】というキーワードが何度も出てきます。
現代の人はいきなり、神様に願ってしまうのですが、神様の方では、
願いを叶えるのは、条件つき
なのです。ゲームと同じで、【神様の神殿】に進むためには? 中ボス倒して、アイテム獲って、そのアイテムを正しい場所にはめ込んで……全ての条件が揃ったときのみ、初めて『封印の扉』が開き、神様に謁見できる。 神様に願いを言うのはその後!
冠婚葬祭の服装や儀式といった、人間同士が作ったルールは守るのに、神が作ったルールは無視して、神社の神域にズケズケ入り込んで、パッと願い事を言って、おみやげコーナーに直行とはどういうことか??
 『神社の作法』について、神様から示された答え!!
ここに載っている内容は「願い事の叶え方」について、人間が勝手に改変する前の『古来の作法』です。
神主さんや神社マニアですら知らない、本物の『神社の作法』!
『神社の作法』について、神様から示された答え!!
ここに載っている内容は「願い事の叶え方」について、人間が勝手に改変する前の『古来の作法』です。
神主さんや神社マニアですら知らない、本物の『神社の作法』!
 『カタカムナ』 全80首の意味−第18句の解説
『カタカムナ』 全80首の意味−第18句の解説